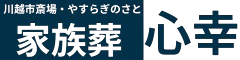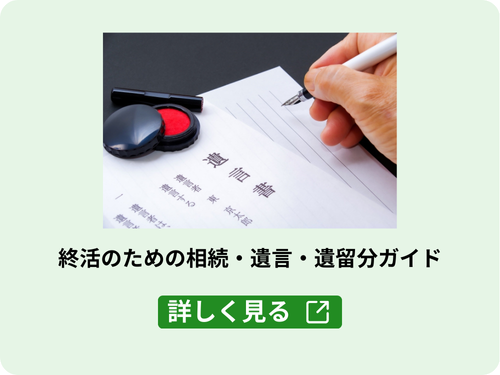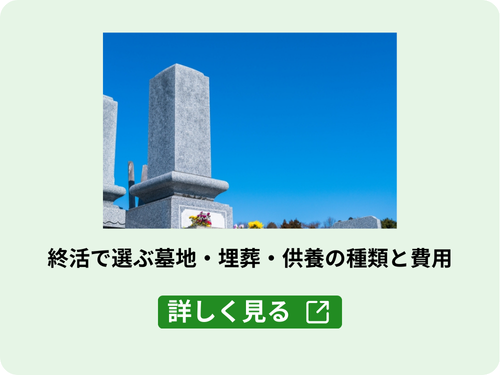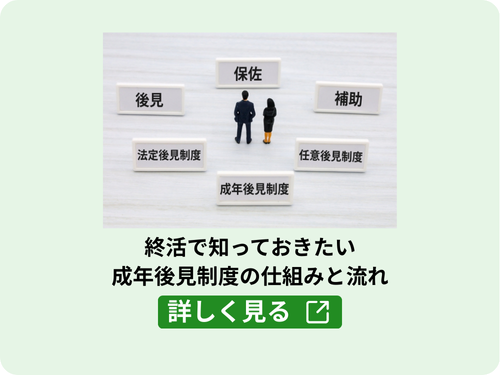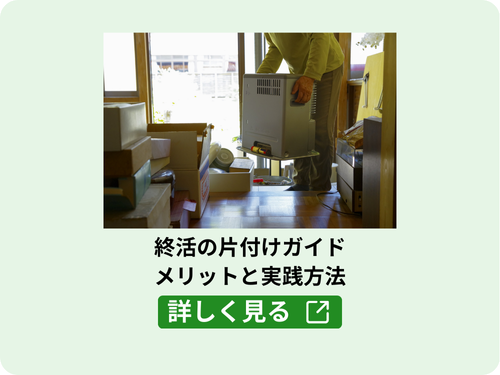終活の社会性 ~終活が必要となる背景を確認しよう~
川越市の葬儀・終活サポート「心幸」では、終活が社会的に求められる背景を整理し、
わかりやすく解説します。
人口構造の変化や核家族化、一人暮らしの増加など、
現代社会の課題を知ることが「なぜ終活が必要なのか」を理解する第一歩です。

終活の社会性 ~終活が必要となる背景を確認しよう~
川越市の葬儀・終活サポート「心幸」では、終活が社会的に求められる背景を整理し、
わかりやすく解説します。
人口構造の変化や核家族化、一人暮らしの増加など、
現代社会の課題を知ることが「なぜ終活が必要なのか」を理解する第一歩です。

(一般社団法人 就活協議会認定)
当社社員は「終活ガイド資格1級」を取得しており、終活に関する専門知識を持っています。
具体的には以下の分野です。
こうした分野について、安心して相談できる体制を整えています。
まずはご自身やご家族の状況に合わせた準備から始めることが可能です。
1. 少子高齢化と人口減少
日本の人口は2010年をピークに減少を始めました。戦後間もない頃、65歳以上の高齢者は人口の約5%に過ぎませんでしたが、現在は28%を超え、2065年には約40%が高齢者になると予測されています。
さらに、75歳以上人口も大きく増加し、2065年には人口の4人に1人が「後期高齢者」となる見込みです。団塊世代が一斉に高齢化することで、介護や医療の負担は社会全体に広がっていきます。
2. 平均寿命と健康寿命の差
日本人の平均寿命は世界トップクラスで、女性はすでに90歳を超えると予測されています。
しかし「健康寿命」との差が課題です。健康で自立した生活を送れる期間は、平均寿命よりも10年ほど短く、介護や医療が必要な「不自由な時間」が長く続くことになります。
「ピンピンコロリ」は理想ですが、現実には病気や認知症を抱えて長く過ごすケースが多いため、老後をどう過ごすかを早めに考える必要があります。
3. 家族のかたちの変化と核家族化
昔は「大家族」が当たり前で、親の介護や葬儀は親戚や兄弟で分担できました。しかし現代は「夫婦のみ」「親と子のみ」の核家族や単身世帯が主流となり、三世代同居は大きく減少しています。
2015年には高齢者のいる世帯が全体の47%に達しました。親戚や地域社会に頼ることが難しくなり、今後は「各世帯が自分のことを準備する」時代になります。
4. 一人暮らし高齢者の増加
2035年には、独身者が人口の約半数に達すると言われています。未婚・離婚も珍しくない時代となり、一人暮らし高齢者の増加は避けられません。
一人暮らし高齢者には、以下のような不安がつきまといます。
5. 終活をしていない場合に起こる問題
終活の準備がないと、突然の病気や認知症、死後の手続きで大きなトラブルが発生します。
終活でできる具体的な準備
| 準備内容 | 具体的な対応例 |
|---|---|
| 👤 身元保証・施設入居 | 信頼できる身元保証人を決める、行政やNPOの保証制度を活用 |
| 💰 財産管理・生活資金 | 財産目録の作成、任意後見契約や信託で管理体制を整える |
| ⚰️ 葬儀・埋葬の希望 | エンディングノートに希望を記録、葬儀社と事前相談 |
| 📜 遺言・相続 | 遺言書の作成で財産分配を明確化、家族に内容を共有 |
| 🐾 ペットの世話 | 引き取り先を決める、ペット信託で資金と手続きを準備 |
こうしたリスクは家族や親族に大きな負担を残してしまいます。
「無縁死」と呼ばれる、引き取り手のないお葬式も年間3万人以上にのぼっています。
6. 終活の準備状況と課題
「終活をしている」と答える人はわずか8.9%。一方で「時期が来ればしたい」と考える人も含めれば、全体の約8割が前向きに考えています。
しかし実際に準備しているのは、お墓や葬儀、エンディングノート程度。財産管理や医療・介護の希望、死後の手続きなど、本当に必要な準備は十分に整っていません。
7. 終活に関わる専門家と支援
当社社員は「終活ガイド上級(1級)」資格を取得しており、終活に関する専門的な知識を持っています。資格に基づき、身元保証・財産管理・葬儀・遺言など、具体的な準備に沿った安心できるアドバイスを提供いたします。

終活は一人ではできません。寺院、葬儀社、弁護士、保険会社、介護施設、不動産会社など、多くの専門家が関わります。信頼できるパートナーと相談しながら進めることで、自分らしい選択肢が広がります。
まとめ:なぜ終活が必要なのか
高齢化・核家族化・一人暮らしの増加という社会の変化により、「自分の最期は自分で決める」ことが重要な時代になっています。
終活は「家族に迷惑をかけない準備」であると同時に、「自分の人生を納得して締めくくる準備」でもあります。心幸は、そのお手伝いをいたします。
▼ 次のステップ
終活の具体的な準備については、以下のページで詳しくご紹介しています。



お見積もり・葬儀の資料をお送りします